愛するプリシラをドイツに残して帰国したエルヴィス・プレスリーは、待っていたロックンロールのファンに応えるかのようにアルバム『エルヴィス・イズ・バック』をリリースして大ヒットさせます。エルヴィス・カムバックのメッセージはエルヴィス登場の時と変わらズシンプルでした。
プリシラに想いを馳せながら

アメリカを表現するカルチャルアイコンとなったエルヴィス・プレスリーが、アメリカがなにをめざしているのかを表現するものだったのか?
50年代ロックンロールが生まれた時、若い世代は戦争に勝って郊外に家を買って平和に暮らしたいと願っていた親世代に対する反抗からだった。権力者は偏見と差別を作り出し利用する。60年代になるとエルヴィスは、優れたバラードを連発して王道に向かう。もっとも的確に表現したのは映画『燃える平原児』(録音は前年60年・販売は61年)だった。インディアンの母親と白人男性の間に生まれた混血児を演じ死に向かう孤高の若者を演じた。巷は公民権法で騒がしくなっていた。排他的なアメリカ、進歩的なアメリカ、矛盾を呑み込んでいるからこそカルチャルアイコンなのだ。エルヴィスは夢の体現者だった。黒人文化を体現した白人、音楽で白人と社会をつないだ人類史上初の反逆者。一方矛盾するようが、きちんと兵役を務めあげた愛国者としての顔。分け隔てなくポピユラー音楽を愛した愛国のキング。その姿はテイラー・スウィフトやドリー・バートンに受け継がれている。

この愛をいつまでも /There’s Always Me

<この愛をいつまでも /There’s Always Me>は、<サレンダー>から<ブルー・ハワイ>まで進化が目覚ましい怒涛の年になった1961年6月にリリースされたアルバム『歌の贈り物/Something For Everybody』に収録された曲。

<知りたくないの>で知られる北京生まれのドン・ロバートソンがエルヴィスのために作ったしっとりと歌い上げるバラードである。67年8月に<ジュデイ>をB 面にして、シングル・カットされてスマッシュ・ヒットしている。また、79年にはカントリー界の大物として、もうすっかりおなじみ、レイ・プライスがカントリー・チャートで30位を記録したほかジム・リーヴスもレコーデイングしている。
ゼアズ・オールウェイズ・ミー/There’s Always Me
吹きこみから7年・・・1967年になって、ようやくシングルリリースされた<この愛をいつまでも /There’s Always Me>は、いまでは、原題そのままに<ゼアズ・オールウェイズ・ミー>とカタカナにしているようだ。
<この愛をいつまでも>の方がなじみがいい。聞いただけで分かる内容で、そのままリスナーを裏切らない。あまりにも意外性がなく単調に聞こえるが、時間も短く、バラードらしいバラードのいい歌だ。
50年代中盤、エルヴィスの若々しく、荒々しい刹那さは陰を潜めたが、誠実さが前面に出ている。
夜の帳が降りて
だれかと電話で
お喋りしたい時
いつも僕がいる
君が恋に破れて
友達が恋しい時
たとえ恋人でなくとも
いつも僕がいる
ちっとも構わないさ
脇役でいることなど
いつか、僕が必要になる
その日がきたら
この腕の中で教えてあげる
出会いと別れをくり返した君に
僕のこの愛は
永遠だと
君の回りを見渡せば
いつも僕がいる
詩がいい、エルヴィス・プレスリーらしく一歩引いてそっと見守る恋歌。大傑作<愛しているのに>や、エルヴィスが70年代にカヴァーした<明日に架ける橋>につながる「この心いつまでも」。聴く人はいまでもその心に哭く。
♪ ゼアズ・オールウェイズ・ミー、いつでもそばにいる心。
♪ 君が恋に破れて
友達が恋しい時
たとえ恋人でなくとも
いつも僕がいる ♪
我慢ではない。励ましだ。
素朴な励ましに、エルヴィスの声が似合う。それが胸を打つ。
「おもしろい人が好き」と女性はいう。
でもその本当は、いっしょに笑ってくれる人のこと、別におもしろいことをいうことでない、一緒に泣き喜び、人生を分かち合ってくれる人。
その向こうにはいつも励ましがある。励ましこそ愛の本体だ
THERE’S ALWAYS ME
When the evening shadows fall
And you’re wondering who to call
For a little company
There’s always me
If your great romance should end
And you’re lonesome for a friend
Darling, you need never me
There’s always me
I don’t seem to mind somehow
Playing second fiddle now
Someday you’ll want me, dear
And when that day is here
Within my arms you’ll come to know
Other loves may came and go
But my love for you will be
Eternally
Look around and you will see
There’s always me
エルヴィスはいつもひとりだった
ビートルズのジョージが言っていた、
ぼくたちは結びつきの強さに自信があった、エルヴィスと違って四人が一緒だった。エルヴィスは一人だからいつも気の毒に感じた。仲間はいたけど、エルヴィスは一人だし、彼がどんな気持ちでいたのか解らなかった、僕たちはなんでも一緒に体験できた。」と気持ちを察していた。1967年のことだ。しかし、エルヴィスは生まれてからずっとそうだった、おそらくエルヴィスがビートルズの一員だったとして、ひとりだっただだろう。

エルヴィスは、死産で亡くなった双生児の兄弟を思いながら過ごす孤独なこどもだった。
母グラディスに対してもそうだった。グラディスはエルヴィスを懸命にケアしたが、グラディスをケアしたのはエルヴィスだった。グラディスが亡くなったあと、変わるようにその座に座ったのはプリシラだった。
愛することと、愛されること、ケアする違いが解らないエルヴィスの柔らかい心は、愛を歌の中に留まったままだった。全てと言っていいほど魅力的なバラードだが、エモーショナルな効果を引き出す技巧にかかっているものだが、エルヴィスの場合、それを嫌った。ではなによって、エルヴィスは歌っているのか。エルヴィスはキング・オブ・ロックンロールだった、しかし672曲のうち、ロックと判断できるのは60曲しかない。一方、ゴスペルは93曲もある。白人社会には、ゴスペルには白人子女を冒涜するアフリカ文化の趣があるがエルヴィスは気にもしかなかった。
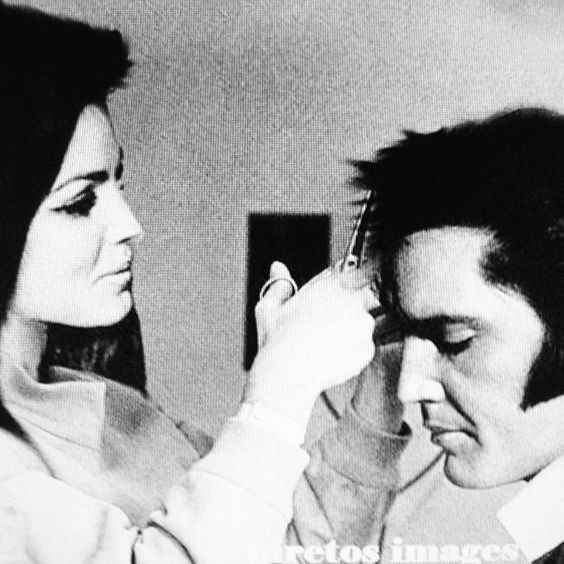
僕はエルヴィスのバラードの引き金は、「安心」だと思う。
怒涛の56年もそうだった。立て続けに放ったロックンロール・メガヒッツのあとにリリースしたのが、エモーショナルな効果を引き出す技巧に無縁のほとんどアカペラの<ラブ・ミー・テンダー>という選択だった。ここにエルヴィスの真髄がある。


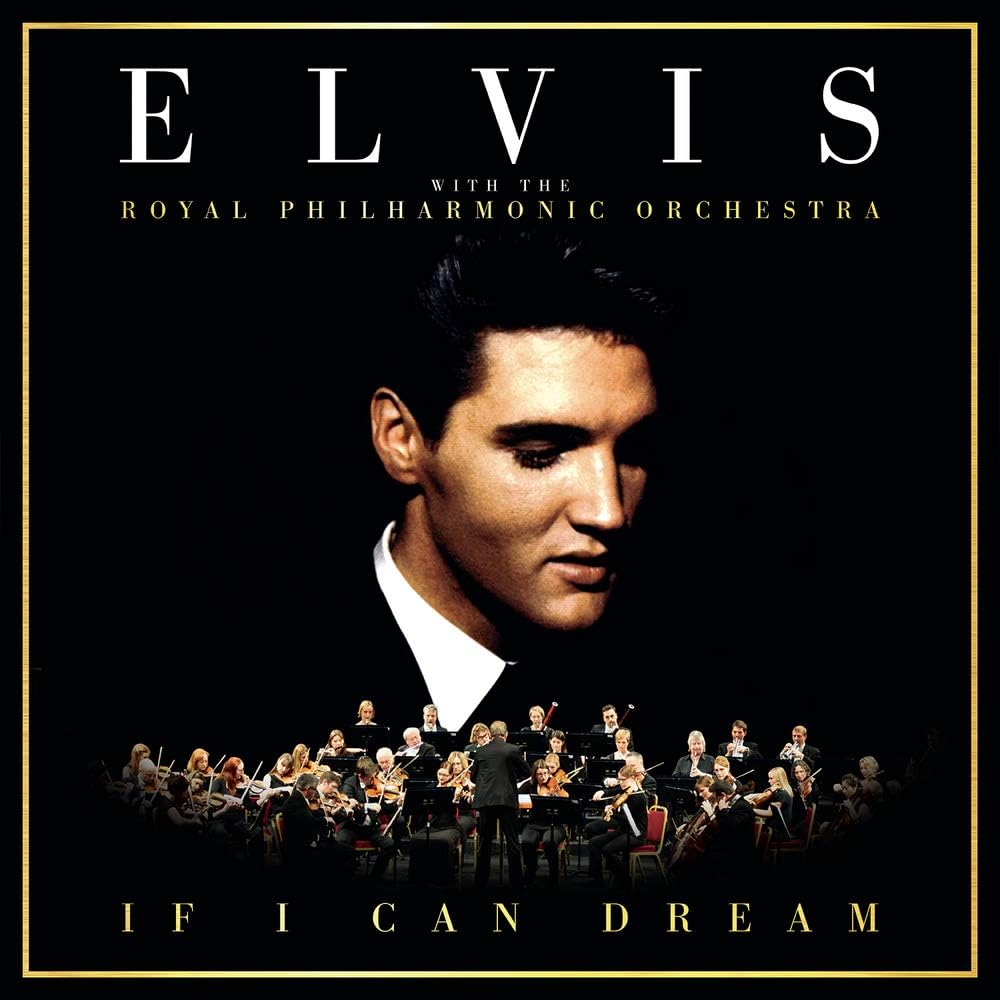
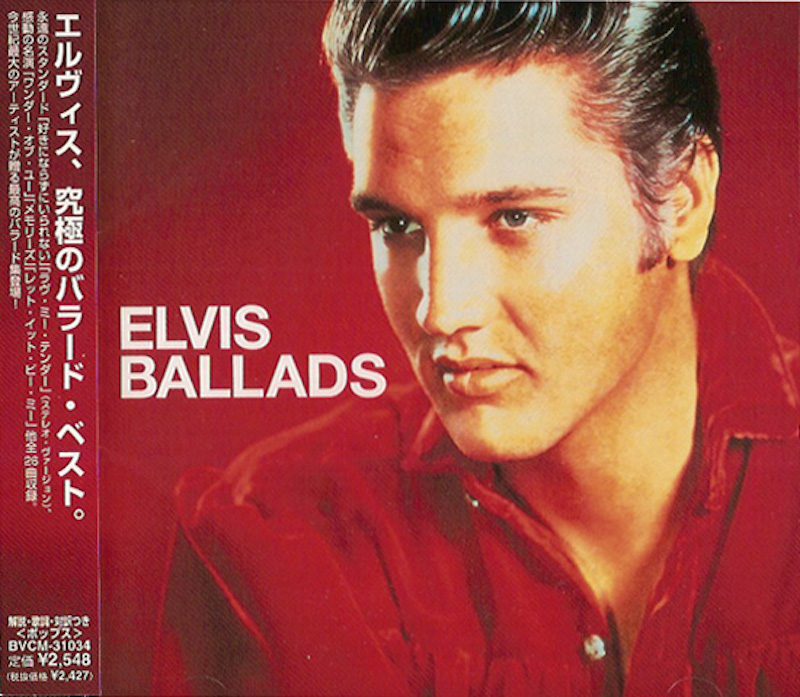


コメント